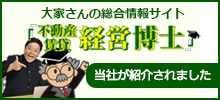賃貸経営塾
-
No.21 「お客様に“お得感”を 感じていただく工夫」
甲乙付けがたい商品を前に迷ったとき、ちょっとした理由で「どちらか」を選ぶことがあります。それは、ほんの少しの「お得感」だったりします。オーナー様のお部屋にも、そのような「お得感」を用意しておくのは、空室対策の一手(ひとて)になるはずです。実は、このシリーズで紹介した「カスタマイズできる部屋」も「家具や家電がセットされている部屋」も、「お得感」を与えるのが目的のひとつでした。
-
No.20 「賃貸経営と高齢化問題」 ~孤立死は防げるのか~
我が国の少子高齢化に伴って、賃貸物件でも入居者の高齢化が進むと思われます。
そこで懸念されるのが、孤独死・孤立死の問題です。ニッセイ基礎研究所の調査によると、死後4日以上経過して見つかった65歳以上の高齢者の数は年間1 万5,603 人(2009 年のデータ)だったそうです。 -
No.19 空室対策は4つのケースで考える
「空室対策」のために、建物や設備を修繕したり、グレードアップさせる工事を検討するときが必ず訪れます。そのときにオーナーは、「やるかやらないか」で迷うことでしょう。
何百万円、場合によっては数千万円の投資になるので失敗したら大変です。もしタイムマシンがあるなら、未来に行って成功を確認してから決断したいものですが、残念ながらタイムマシンは、まだ発明されていません。 -
No.18 日頃のメンテナンスとコストのコントロール
空室対策といえば何を思い浮かべるでしょうか。「家賃を下げる」、「リフォームする」、「礼金・敷金をゼロにする」等の方法ではないでしょうか。でも一番大切なのは「日頃のメンテナンス」です。
「空室を発生させない」ためにも「収益を確保する」ためにも「日頃のメンテナンス」と「コストのコントロール」が重要です。 -
No.17 立退き料を考える
賃貸経営にとって「立退き料の負担」は最後に待ち構える大きなリスクです。
建物は老朽化により取壊しをしなければならないのが宿命で、その時点の入居者に退去のお願いをしなければなりません。そのとき、立退き料が発生します。
その負担を避けるには、途中で売却するか、全部屋が退去するまでじっと待つしかありません。
その選択肢があり得ないときは、負担をゼロに近づける努力を計画的に行っておく必要があります。 -
No.16 賃貸経営の通信簿とは
賃貸経営の評価として「投資に対してどれだけ収益があがっているか」という物差しがあります。
賃貸経営は不動産投資ですから、当然に収益(リターン)を求めるべきですね。たとえ賃貸経営を始めたキッカケが税金対策や土地活用のため「仕方なく」だったとしても、経営を始めた以上は「最大の収益」を求めたいと思います。 -
No.15 閑散期の空室対策の考え方
賃貸の繁忙期と閑散期とは何でしょうか。
春と秋に多くの空室が供給され、一方で大勢の入居希望者が部屋を探します。それで忙しいので繁忙期と言うのですが、これは不動産会社から見た呼び名ですね。 -
No.14 現代の借主の意識とニーズとは
「物件の価値を高める手段」について
そのために必要な「借主の意識とニーズ」を知るべし -
No.13 好きな部屋なら永く暮らしたい
前回は「借主の意識とニーズ」を考えてみました。
結論として、借主が「自分好みの部屋を選びたい」と考えているという実態を紹介させて頂きました。
そこで今回は「自分好みの部屋」について、もう少し具体的な事例を挙げてみることにいたします。 -
No.12「収益計画」のすすめ
賃貸経営には、オーナーごとにそれぞれの目的があります。
あるオーナーは「節税対策」で賃貸経営を始めます。固定資産税や相続税などがその対象です。
特に相続税対策で賃貸住宅を建てるオーナーは多いですね。相続税は平成27年からの増税になりますので、対策の見直しを迫られるオーナーも多いのではないでしょうか。
また「土地を維持するため」という目的のオーナーもいらっしゃいます。親から受け継いだ土地を易々と手放すわけにはいきませんが、土地は「何も活用しないまま」所有することを許してくれません。固定資産税の負担が重いからです。
計算上は60年以上払い続けると、その支払い累積額が土地の価格を超えてしまうこともあるほどです。仕方なく賃貸経営を始めるオーナーもいらっしゃるのではないでしょうか。
一方で「資産を増やす」ことが目的で賃貸経営を始めるオーナーもいます。不動産投資家と呼ばれる方たちです。