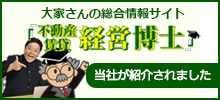ワンポイント税務
-
2025年12月 大家さんのための税金基礎講座
インボイス制度2年目の確定申告!「2割特例」の有利不利と、2027年以降の戦略的判断
2025年も師走を迎え、来春の確定申告(2025年分)に向けた準備を始める時期となりました。
インボイス制度の開始(2023年10月)に伴い課税事業者となったオーナー様にとって、今回の申告は「2回目」の消費税申告となります。
前回の申告(2024年分)では、計算の簡便さから「2割特例」(売上税額の2割を納付)を選択された方も多かったのではないでしょうか。
しかし、この特例は経営判断を停止させるものではありません。
今回は、2025年分の申告における「2割特例」の有利不利の検証と、特例が終了する2027年以降を見据えた経営戦略について解説します。
1 2025年分。「2割特例」と「本則課税」どちらが有利か?
まずは、2025年(今回)の申告における選択肢の「検証」です。
2025年分申告:納税額の計算方法比較方式 ①2割特例(簡易的な計算) ②本則課税(実額で計算) 計算式 預かった消費税
×(かける)
20%預かった消費税
―(マイナス)
支払った消費税特徴 ・事務作業が圧倒的に楽
・売上さえ分かれば
計算できる・仕入(経費)が多いほど納税額が減る
・インボイスの保存
・集計が必須判断 経費が少ない年に有利 大規模修繕など高額な支払いがあった年に有利 (還付の可能性も)
<現場での判断ケース>
もし2025年中に、高額な外壁塗装や給排水設備の交換といった大規模修繕を行った場合、どうなるでしょうか。
支払った修繕費に含まれる消費税が非常に大きいため、「本則課税」で計算したほうが、「2割特例」よりも納税額が少なくなる(あるいは還付になる)可能性が出てきます。
特に、インボイス番号のある業者へ多額の支払いがあった年は、「計算が楽だから」という理由だけで2割特例を選ぶと、キャッシュフロー上は損をしているかもしれないのです。
2 要注意!「2割特例」は2026年分で終了します。
2025年分の検証と同時に、さらに重要な経営判断が迫っています。
それは、2割特例が「2026年分(2027年3月の申告)」をもって終了するという事実です。
2027年分以降、オーナー様は「本則課税」か「簡易課税(※課税売上が5,000万円以下の場合に選択可)」のどちらかを選択し、消費税を計算・納付しなければなりません。
「簡易課税」は、業種(不動産業は第6種)に応じて「みなし仕入れ率(40%)」で計算するため、事務負担率は軽いですが、本則課税と比べて必ずしも有利とは限りません。
2割特例の適用期限(タイムライン)
~2024年分(前回) ▶ 2025年分(今回) ▶ 2026年分(次回)
ここまで「2割特例・本則課税・簡易課税」から選択可能
重要! 2027年分(2028年3月申告)~ 「2割特例」 終了!
本則課税 か 簡易課税 の選択が必須に
3 「今」やるべきこと。2027年を見据えた修繕計画
2割特例が終了するからこそ、修繕計画も「税務戦略」して捉えなおす必要があります。
本則課税が有利なオーナー様
駐車場・テナント収入の割合が高く、今後も定期的に大規模修繕を行う予定がある場合、2027年以降は「本則課税」を選択する方が有利になる可能性が高いです。
修繕時期の最適化
例えば、大規模修繕を2026年中に実施すると、まだ「2割特例」を選んでいる場合は高額な仕入税額控除(支払った消費税)が使えません。
あえて修繕時期を2027年以降にずらし、その年から「本則課税」を選択して高額な消費税の還付(又は納税額の圧縮)を狙う、というのも有力な経営戦略です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
消費税の申告は、単なる事務作業ではありません。
ご自身の物件ポートフォリオ(課税売上の比率)と、長期修繕計画をどう組み合わせるかという、高度な「経営判断」そのものです。
「2025年分の申告で本則課税に切り替えるべきか?」
「2027年以降の修繕計画をどう組むか?」
こうした判断は、物件ごとの状況によって最適解が異なります。
ご不明な点は、ご契約の管理会社と物件の収支や修繕履歴を確認の上、顧問税理士にご相談ください。
※本稿は2025年10月時点の制度を前提とした一般解説です。
最終的な税務判断については、必ず顧問税理士等の専門家にご確認ください。