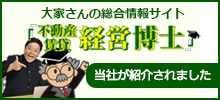ワンポイント税務
-
2025年8月 大家さんのための税金基礎講座
「小規模宅地等の特例」を活かすには
相続対策の中でも、不動産オーナーに大きな影響を与えるのが「小規模宅地等の特例」です。
この制度は大きく分けて3 つに分類されます。
利用区分 上限面積 減額割合
①特定居住用宅地 (自宅) 330㎡ 80%
②特定事業用宅地
(店舗・工場など、自己で事業に使用している土地) 400㎡ 80%
③貸付事業用宅
(アパート・駐車場など、第三者に貸し付けている土地) 200㎡ 50%
いずれも、条件を満たして適切に活用すれば、相続税評価額を大幅に引き下げることができます。
相続財産に一定規模の宅地等が含まれている場合には、数百万円から、場合によっては数千万円単位で相続税を抑えられる可能性もあります。
また①自宅などの特定居住用宅地と②店舗などの特定事業用宅地の両方に該当する場合は、併用が可能で、それぞれの限度額まで適用可能です。
なお、特例の併用にあたっては、「どの宅地に何㎡まで適用できるか」という上限が決まっており、③アパートなどの貸付事業用宅地が含まれるケースでは、①特定居住用宅地や②特定事業用宅地と異なる複雑な面積制限が設けられています。
特例の効果を最大限に活かすためには、3つの中から「どれを選んで適用するか」「どこまで使うか」といった判断が求められます。
例えば: 評価額が非常に高い都市部のアパートが対象であれば③貸付事業用宅地を優先した方が有利になることもありますし、①特定居住用宅地と②特定事業用宅地だけを活用した方が結果的に節税額が大きくなるケースもあります。
このように組み合わせによって結果が大きく変わるため、最終的には税理士など専門家の試算を通じて判断することが重要です。
地方オーナーでも「小規模宅地等の特例」を活かせる可能性がある?
小規模宅地等の特例は「対象面積の上限」があるため、「評価額が高くて面積の小さい都市部の土地」ほど制度のメリットを活かしやすく、逆に「評価額が引くて広い地方の土地」では節税効果が限定的になりがちです。
しかし、ある工夫をすることでメリットを活かすことができる可能性があります。
それが、「等価交換(不動産交換特例)」という制度を活用する方法です。
そもそも「等価交換(不動産交換特例)って何?
簡単にいうと、自分の持っている宅地等と、他人が持っている宅地等を“等価”で交換することです。
例えば: ■地方にある「坪単価が低く」て広い宅地等」(例:1000 ㎡、坪単価10 万円)
■都市部にある「坪単価が高くて狭い宅地等」 (例:200 ㎡、坪単価50 万円)
を、価値が釣り合う形で交換することができます。
このとき、「不動産交換特例」を使えば、通常の売買であれば発生する譲渡所得税(売却益に対して課税される所得税・住民税)を、その時点では課税せず、将来的に売却などを行ったときまで繰り延べることができる仕組みです。
つまり、課税が免除されるわけではありませんが、現時点で納税を回避でき、資金繰りや節税対策を柔軟に行える点が大きなメリットです。
現実的にできるの?
たしかに、実務上は「交換相手がいるか?」「税理士や専門家のサポートが必要か?」といったハードルがあります。
しかし、将来の相続や資産承継を見据えて、“節税を意識した不動産の組み替え”を行うことは、納税負担を軽減しつつ、資産の収益性や流動性を高めるうえで非常に有効な戦略といえます。
小規模宅地等の特例が適用できないリスクに注意
「小規模宅地等の特例」は非常に有効な節税制度ですが、条件を満たしていなければ適用されません。特に近年は税務署による審査も厳しくなっており、単なる形式要件だけでなく、実際に賃貸事業が継続されているか、相続人に事業継続の意思があるかといった“実態”が重視される傾向にあります。
例えば、長期間の空室やリフォームなどで一時的に賃貸が停止していた場合、「実際に貸していなかった」と判断されることがあります。
また、土地が法人名義である場合は制度の対象外となり、さらに相続発生後すぐに売却や建物の解体を行った場合も、「継続利用の意思がなかった」とみなされ、特例が適用されない可能性があります。
「うちは問題ないだろう」と思っている方こそ、こうした細かな落とし穴には十分に注意が必要です。相続は、準備次第で大きく結果が変わります。特例を活かすためにも、詳しく税理士さんに相談して今から備えておきましょう。