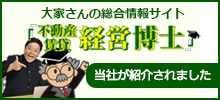業界ニュース
-
2025年12月 賃貸業界のニュースから
「みんなで大家さん」投資リスクと「住環境」が招く健康問題
2000億円の巨大ファンド 「みんなで大家さん」が配当停止
「年利7%、元本償還」を謳い文句に、多くの個人投資家から2000億円を超える資金を集めてきた不動産ファンド「みんなで大家さん」が、現在大きな問題に直面しています。
約束の配当金が3か月以上も遅延し、開発計画は度重なる延期。全国では集団訴訟が進行しており、賃貸経営に関わるオーナーにとっても決して無関係な話ではありません。
問題の発端は、千葉県成田市の大規模開発プロジェクトです。
出資者は同商品購入で投資し、収益を配当として受け取り、5年満期後に出資金が全額返還される予定でした。
しかし、工事の遅れが常態化し、2025年に入るとついに複数のファンドで配当金の支払いがストップ。この事態に出資者の動揺が広がっています。
所管する自治体は、不動産特定共同事業法に基づき処分や指導を実施。説明不足や不適切な契約表現など、運営側の情報開示姿勢に厳しい視線を注いでいます。
なぜ、こうした事態に至ってしまったのでしょうか。
投資家の多くは取材に対し、「過去の実績を信じた」「中身や仕組みをよく調べずに投資した」と、見通しの甘さを口にしました。
開発プロジェクトは成田空港近郊で、東京ドーム10個分の広大な用地にホテルやアリーナなどの大規模な商業施設を開発する計画です。これは難工事が予想され、なおかつプロジェクト成功の見込みも不透明です。
こうした不動産開発特有のリスクを直視せずに、単なる金融商品として見てしまったのでしょう。
また、もともとの法律の不備も指摘されています。経済誌の記者は次のように指摘します。
「プロジェクト用地は周辺相場の100倍以上という以降な高評価で販売されていた。関連会社間の資金移動など、出資者に見えにくい運用リスクを高めている。制度的な法改正を含め、情報開示や監督体制の強化が必須になるはずだ」
とはいえ、肝心の出資金回収は見通しが立たず、多くの個人が不安を感じながら過ごしています。すでに1000人以上が出資金の返還を求め、裁判に移行する予定と報じられています。
賃貸オーナーにとっても、投資リスクの見極めという意味で、他山の石とすべき事例と言えるかもしれません。
教訓は明快です。高利回りの背景には、必ず一定のリスクが潜むということ。やはり事業の実態や資金の流れ、契約内容まで丁寧に確認し、「自分が理解できない商品には手を出さない」という原則を貫くべきでしょうか。
「みんなで投資しているから安心」ではなく、「最終的な責任は自分が背負う」という意識が、投資判断には不可欠です。
住宅の質が命を左右? 賃貸マンションと心血管リスクの関係
最近の研究で、住宅の種類や所有形態が高齢者の健康に影響を与えることが明らかになりました。
東京科学大学などの研究チームが、日本各地の65歳以上の高齢者約4万人を6年間追跡した結果、分譲マンションに住む人と比べて、賃貸マンションの居住者では心血管疾患による死亡リスクが約1.8倍高いことが分かりました。特に男性では2倍を超える差が見られたといいます。
その理由として、住宅の「質」の違いを指摘しています。分譲マンションに比べて賃貸住宅は断熱性や気密性が劣る傾向にあり、冬季の室温が低く不安定になりやすい。室温の変動が大きいと血圧も変動し、それが長期的に心血管リスクを高める要因になるというのです。
心血管疾患は突然死や孤独死、事故物件の要因にもなり得ます。断熱や遮音、温度管理など住環境の改善は、入居者の健康維持だけでなく、長期入居や信頼性の向上にも寄与しそうです。
賃貸住宅オーナーにとっても室温の温度管理はプラスの面が多いようです。
例えば二重窓(内窓)の設置や、浴室暖房乾燥機の導入、高効率給湯器への交換といった比較的導入しやすいリフォームが、ヒートショック対策(=事故物件リスクの低減)の第一歩となるかもしれません。
日本全体で高齢化が進むなか、温かい部屋づくりは入居者の命を守ることに貢献するのかもしれません。